人類史上最大の発展を遂げた割には、幸福度が高まっていかない昨今。
寿命は延びつつありますが、メンタル問題はますます増えていく。
そんな世の中を生きていく子どもたちにどんな授業をしていけばいいのかな〜と悶々と考えているのですが、先日参加した研修会で、忘れたくない事があったのでメモ。
ざっくり言うと「これからの教育は、さらに個別化していくよー。」という内容でした。
有識者によれば、次期指導要領改訂のポイントはいくつかあれど、「GIGAスクール構想をさらに推し進め、情報活用能力にコミットすること」は間違いなく謳われるとのこと。
確かに、GIGAスクールの実現によって教育は一新しましたからねー。
もちろん、新しい問題も生まれましたが、メリットの方が大きいというのが現場の実感知。
従来の「みんなで」から脱却し、「学習の個別化」が実現できる下地は整いました。
ただ、個人主義に偏りすぎると危険だよなーとも思うのです。
本記事では、「個別化が進む社会において、学校はどんなことに気をつけないといけないのか?」を話題としています。
先生や子どもだけでなく、全ての人に関係しますので、お時間許すのであればさくっと読んでみてくださいね。

加速する個別化
私が子どもだった頃は、テレビ番組のチャンネル抗争がお決まりの日常でした。
その背景には、「学校で友達と共有したい!」という切実な思いがあったのですが、理由があれど簡単に譲ってはくれません。
そんな風景は、過去のものになったみたい。
一人一台端末が普通になった今や、テレビ以外の選択肢が豊富にあり、争ってまで権利を獲得する必要がなくなりました。
同じ部屋にいるけれど、みんなが別々の媒体を使っている状態が令和のリビングでしょう。
さらに、消費してもらうメディア側も「その人」の傾向を分析し、その人に適したしたコンテンツを提供してくれる。
それはそれは、ありがたいサービスです。
そして、教育界でもこのような「個別化」は進んでいます。
先日の研修会では、「オーダーメイド教育」なんて言葉が出てきましたが、これは、既に行われている過去のもの。
もちろん、個に応じた学習環境が整うことは、間違いなく学習効果を上げるでしょうが、そっち側に偏り過ぎるデメリットも意識しておくべきだと思うのです。
個別化のデメリット
個別化が進んだ現代社会を生きる子どもや保護者と話をしていると、「興味がないからやらない」とか「うちの子は、もっと違う方法で学ばせたい」なんて言葉が当たり前に聞かれるようになりました。
もちろん、目標に向かって個人で学習していく力は生涯役立つ能力なので、どんどん挑戦して伸ばしてほしいもの。
ただ、だからといって「他者と一緒にやらない」とか「他人のやっていることなんて興味がない」というのは自分の可能性を狭めかねない。
ひいては、人生という大枠において、その選択がネガティブな結果をもたらすかもしれないのです。
「自分一人で学べる」し、「自分一人で楽しめる」という個別化の加速は、人と関わることのハードルをさらに上げてしまうでしょう。
少し話は変わりますが、日本の少子化問題が懸念されて久しくなりました。
最近では、若者の恋愛離れも加速しているとか。
その要因として、個別化の影響を抜きに語ることはできません。
自分の決定権によってコントロールできる生活は、短期的に見れば心地良いのは分かります。
ただ、長期的に見れば、多少のストレスはあれど、人間関係を醸成するコミュニティの所属は欠かせません。
幸福度を左右する最も強い要因は「人間関係の充実」ですからね。
学校の価値
「勉強って何の意味があるの?」
「わざわざ学校で勉強する意味ある?」
子どもからこの質問をされる回数は、ここ数十年間で確実に増えました。
不登校の人数が過去最多なんて話題となっていましたが、その要因として、「学校に行かなくても勉強ができる」とか「学校では自分が勉強したいことを教えてくれない」という選択して学校へ行かない子どもも少なからずいます。
「学び」という面では、最高に充実した現代において、「学校の価値って何だろう?」というのは、問い続ける必要があるでしょう。
その答えの一つとして、
「考え方の違う他者との関わりによる成長」
は、欠かせません。
テストの点数を取るための勉強であれば、点数の取り方を教えてくれる環境を選択した方が効率が良いのは確実です。
ただ、自分が正しいと思っていた価値観を揺さぶれるような出会いというのは、ランダムな人間関係からしか生まれません。
個別化の加速は、「自分にとって心地よい刺激を選択して受け入れていく」という側面があり、ともすると、価値観の固定化が進んでしまうかもしれません。
怖いのは、自分が選択した心地良い情報ばかりに触れていると、自分の価値観の固定化に気づくことができないこと。
価値観の固定化により、視野が狭くなると、成長チャンスを逃すことにつながります。
もちろん、学校から「つまらない」とか「合わない」といったコンテンツを提供されることもあるでしょう。
ただ、「自分が好きなことに取り組む」という安心感も確かに大切ですが、「最初は気が進まなかったけど、やってみたら楽しかった」という出会いがあることもあります。
そんな出会いを演出できるのも、学校の価値なのです。
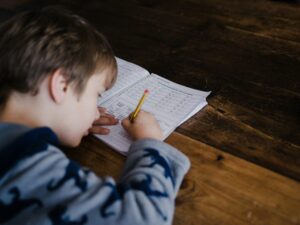
まとめ
本記事では、「個別化する社会において学校の役割って何だろう?」という内容を書きました。
「学習」という点においては、個人で進めることはできますが、「人間が介入した方が上手くいくよ」ということも分かっています。

もちろん、先生側が改善していく面も多々あるでしょう。
ただ、「勉強はつまらないものだ」と決めつけて、やってみる前に拒否するのはもったいない。
多様な性格をもつ人間ですから、スタートラインに立つだけで、得意・不得意の個人差はあるでしょう。
ただ、不得意だから嫌いとするのはもったいない。
「算数が嫌い」みたいな抽象度高めのまま放っておくのではなく、もっと具体化した得意・不得意を見つけ出すことは、自分理解を深め、今後の人生に役立つ選択を生み出すかもしれません。
そんなサポートができる場所として、学校が成立したらいいなぁと思う今日この頃でした。








コメント