教室で子どもたちと勉強をしていると、様々な気づきがあります。
数年前から非認知能力が話題となり、「やっぱり粘り強く取り組む子どもは、勉強ができるよなぁ」と改めて感心しているのですが、そもそも「粘り強さってどうやって発揮されるの?」と気になったので調べてみました。
もちろん、複数の要因があるにしても、「意志の力」は、外せません。
某ジブリの宮崎氏も「大切なことってのは、大抵めんどくさい」的なことをおっしゃっていましたが、勉強も然り。
やらないより、やっておいた方が良いにも関わらず、「やらない」という結果になってしまうのは、やはり「めんどう」という理由が大きいのではないでしょうか。
そんな「めんどう」に立ち向かう時、「意志力」が助けとなるのです。
そんな意志力ですが、「使っても減らないかも」みたいな話題を書きました。
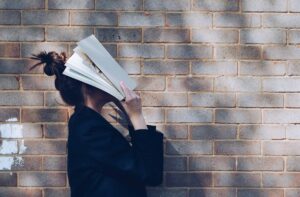
その前提に立った上で、「どうすれば上手に発揮できるのか?」について、情報をシェアします。
意志力を「機会費用」と考えてみよう
意志力について考える上で、「意志力ってのは、機会費用なんじゃない?」という主張がおもしろい。
→こちらの研究
「機会費用」というのは、経済用語で、「ある行動を選んだために得られなくなった価値のこと」です。
世の中は、トレードオフですから、何かを選んだら何かを選べなくなるわけで。意志力もそんな側面があるのではないかという目から鱗情報です。
ざっくりまとめると、
何かをするという行動選択には、意志の力が働いており、その強さは、「選んだ行動」に対する自分自身の考え方によって上下する
ってこと。
例えば、夕飯前に宿題へ打ち込んでいるとしましょう。
宿題の問題がスラスラ解けているときは、集中して取り組んでいる模様。
しかし、難問にぶち当たったところで戦況が変わります。
「あれっ、解けないかも」と負荷がかかったとたん、「お腹すいたから先に夕飯を食べようかな」みたいな衝動が生まれる。
このようになった状態を「宿題」と「夕飯」という選択がトレードオフ状態で戦っていたと考えると意志力の働き方が見えてきます。
最初は、問題をスラスラ解けたので、勉強に対する意志力も小さめ。
しかし、難問にぶち当たると「止めたい」という気持ちが大きくなるので、「勉強を続ける」という選択をするためにより大きな意志の力が必要になるでしょう。
だからこそ、「勉強を止めて夕飯を食べる」という意志力を温存できるような選択肢に意識が向いていく。
最善策は、「宿題を終わらせてから夕飯を食べること」というのは、分かっているにも関わらず、より意志力を消耗しない選択肢の方へ流れてしまうのですよね。

自分の成長をイメージして意志力アップ!!
意志力を「機会費用」と考えることができれば、「自分の成長につながることに意志力を使った方がいいよね!!」ということは自明の理。
・ショート動画を見るよりは、勉強した方がいい。
・だらだらするよりは、運動した方がいい。
・深酒するよりは早く寝たほうがいい。
というように、油断すると流されてしまう状況に待ったをかけるために意志力を使った方が良いのです。
しかし、言うは易く行うは難し。
なぜ、行うは難しかと言うと、
「現在の自分と未来の自分が離れたものとして意識されているから」
に他なりません。
人間の意識は、遠い未来になればなるほど楽観的になるという特徴がありますからね。
先延ばしにしても自分を苦しめるだけなのに、「今」を生きている僕たちは、めんどくさい作業を「未来」の自分に投げてしまうのがあるある。
そんな人間らしさを打ち砕き、自己成長につなげるためには、
「今の自分の選択が、未来の自分の成長につながるんだ!!」
という意識をもち、その意識を意志力に変えるしかありません。
この考え方を勉強に応用するならば、
・この勉強が、テスト100点につながる。
・この勉強をマスターすれば、〇〇ができるようになる。
・この勉強が大人になった時の〇〇につながる。
・これをやっておけば、〇〇という仕事に就いた時に役立つ。
みたいな感じで、「自分にとって必要なスキルとなる!!」という意識で取り組んでもらうことが望ましい。
先生界で、「勉強を自分事としよう!!」「主体的な学習が大切!!」なんて言われるのは、ここら辺にメリットがあるからでしょう。
じゃあ、先生側がすべきことは何だ?と言うと、
・この勉強が生活の中でどのように役立つか?
・この勉強が将来の生活(仕事も含む)でどのように役立つか?
・この勉強は、みんなの生活のこんなところで使われるよー。
というように「スキルを身につける長期的なメリット」をイメージしてもらうことは一役買ってくれることなのかなぁと思います。
意志力を発揮するためには、「未来の自分」と仲良くなろう
最後に意志力を発揮するためにとっても使える「未来の自分ディスカッション」という怪しげな方法を紹介します。
ビジネス界のあるある成功法則として「メンターをもとう」なんて言われますよね。
このメンター効果は、自分が困ったときにその困り感から距離をとり、より客観的な視点で良い判断を下そうというカラクリ。
悩みとか不安って、渦中にいると冷静になれないですからね。
この方法を応用したのが、「未来の自分ディスカッション」。
例えば、「10年後の自分」とか「就職した自分」みたいな感じで未来の自分を設定して相談をする。
「来年の夏、3kg減量した自分」を設定し、「あのさ、どうしてもスイーツ食べたいんだけど、どうかな?」と相談すれば、「いやいやいや、舐めてんの?」と答えてくれるはずだから、食後のデザートを抑えられるかもしれませんよね。
この方法を子どもたちに伝授して、どれだけ伝わるかは未知数ですが、「6年生になった自分」、「志望校に受かった自分」、「夢を叶えた自分」みたいな仮想の自分を設定すれば、きっと未来の自分が「勉強しろ!!」と伝えてくれるのではないでしょうか。
ぜひとも、お試しあれ。









コメント